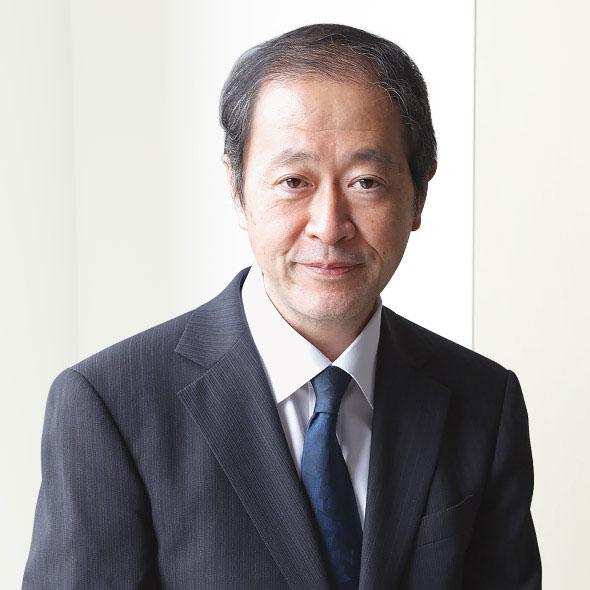- Article Title
- 7月米JOLTSは軟調な結果、利回り上昇は一服
米労働省の雇用動態調査によると、7月の求人件数は市場予測や前月を下回り、特にヘルスケアや娯楽・ホスピタリティー部門で減少が目立った。求人件数と失業者数の比率も1を下回り、雇用環境の悪化が示唆された。米国債市場では超長期国債利回りが上昇傾向だったが、軟調な求人件数、FRB高官のハト派発言などを受け3日の利回りは低下した。9月FOMCでの利下げの確度は高まったようだ。
7月の米求人件数は市場予想を下回り、6月分も速報値から下方修正
米労働省が9月3日に発表した雇用動態調査(JOLTS)によると、7月の求人件数は718.1万件と、市場予測の737万件、6月の735.7万件(速報値743.7万件から下方修正)を下回った。7月の求人件数で減少が見られた部門はヘルスケアと小売り、娯楽・ホスピタリティーなどだった。
7月の失業者に対する求人件数の割合は失業者1人に対し0.99件と節目の1を下回った。失業者に対する求人件数は22年3月の2.02件をピークに減少基調にある。解雇件数は180.8万件と依然低水準ながら、過去3ヵ月は増加基調となっている。転職の活況度を反映する離職率は2.0と前月から横ばいで回復の鈍さが示唆された。
軟調な求人件数などを背景に、最近の超長期国債利回りに一矢報いた
米国債市場では足元、超長期(通常10年超のイメージ)国債利回りと、2年など短期セクターの国債利回りとの格差(スプレッド)が拡大傾向だ(図表2参照)。短期セクターは利下げ期待が利回りの下押し要因となっている一方で、超長期セクターでは財政不安やインフレ懸念などを大きく反映しやすいことがスプレッド拡大の背景だろう。
しかし、3日の米国債市場では①軟調な求人件数に加え、②米連邦準備制度理事会(FRB)高官のハト派(金融緩和を選好)発言、③景気横ばいを示唆した地区連銀経済報告(ベージュブック)の3点セットで国債利回りは超長期セクターが主導する形で全般的な利回り低下が見られた。3日の30年国債利回りは節目の5%突破とはならなかった。利回り上昇を抑制した先の3点セットを簡単に振り返る。
①の求人件数調査では主に次の2点に注目した。まず、7月の求人件数で減少が目立った部門はヘルスケアや娯楽・ホスピタリティーなどであることだ。これまで雇用を支えてきた部門が軟調だったことがは懸念材料だ。もっとも求人件数は変動の大きい経済指標で、単月の結果で判断すべきではない。9月5日には8月の米雇用統計が発表される。この統計も参照して、先の部門の採用に変化がないかなどに注意を払う必要があるだろう。
求人件数調査で気になるもう1つの点は求人数の減少だ。企業の求人数(欠員)が仕事を探している人数(失業者数)の何倍であるかを示す欠員/失業倍率は1を下回った。この関係を求人数(欠員率)と失業率から見て、求人数の低下がどこかの水準で失業率が急上昇させる曲線として描く分析もある(ベバリッジ曲線)。失業率が急上昇する求人件数の水準を予測するには他の要因も関係するため困難な作業だが、直感的にも求人件数が失業者数を下回る状況というのは雇用環境の悪化を反映していると感じられるところだ。
FOMC参加者の発言も9月のFOMCでの利下げ再開をおおむね支持
②のFRB高官発言は、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に金融政策に対する発言を控える「ブラックアウト期間」が週末に始まることから注目されている。主な発言を振り返ると(図表3参照)、8月22日のジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の発言に代表されるように、9月の利下げ再開がメインシナリオとなっている。デーリー総裁の「近く」というのは9月のFOMCでの利下げを示唆しているのだろう。
9月3日の主な発言ではアトランタ連銀のボスティック総裁は年内1回という従来の主張を維持したが、インフレや雇用市場次第では更なる利下げも匂わせており、9月だけの利下げにとどめない考えを示唆した。
最も注目されたのはウォラー理事の発言だろう。来年5月に任期切れとなるパウエル議長の後任候補11人のうちの1人でもあるウォラー理事は9月の利下げ開始を明確に指示するとともに、9月後も複数回の利下げが必要との考えを示した。現在の政策金利が中立金利(景気を熱しも冷やしもしない名目金利)を上回っているからだと説明した。また、どの程度上回っているかについて、ウォラー理事はおおよそ1%から1.5%と指摘した。これはベッセント財務長官の考えに近いと思われる。
一部のFRB高官は利下げに慎重な姿勢を示してはいるが、反対票を投じるほど明確なコメントは、最近影をを潜めたようにも思われる。
③のベージュブックは米国の経済活動が大半の地区で前回の7月上旬時点から「ほぼ変化がなかった」と指摘し、経済活動の鈍化が示唆されたことが注目点だ。ただし、物価については全ての地区で上昇し、10地区では「緩やかないし緩慢な」インフレ、2地区では「投入価格の強い伸び」が報告された。とはいえ、雇用の鈍化に目が向き始めたFOMC高官の流れを止めるものではなく、9月の利下げ再開と、その後の複数回の利下げというシナリオを筆者は想定している。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。