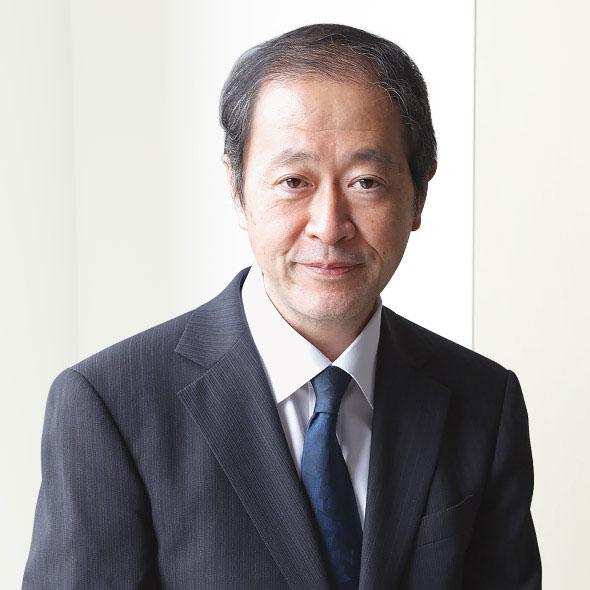- Article Title
- 9月FOMCの議事要旨、利下げながらもややタカ派
9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公表された。年内追加利下げを多くの参加者が支持する一方、インフレ懸念から慎重な意見も見られた。労働市場についてはFOMC前の米雇用統計に悪化の兆しも見られたが、概ね安定しているとみているようだ。バランスシート縮小や政策金利の指標の変更については、議事要旨に検討された形跡は見られないが、引き続き今後の展開に注意したい。
追加利下げ再開となった9月のFOMCの議事要旨にはタカ派の側面も
米連邦準備制度理事会(FRB)は10月8日に、9月16〜17日に開催した米連邦公開市場委員会(FOMC、以下会合)の議事要旨を公表した。この会合では追加利下げが再開されるとともに、政策金利の年末水準を示唆するドットチャートによると大半は10月以降の年内の追加利下げを支持していることが示された(図表1参照)。
議事要旨でも、「大部分の参加者は10月以降の年内の追加利下げを支持」すると記されている。一方で、数名から9月の利下げに消極的な記述も見られた。利下げを決定した会合でありながら、タカ派(金融引き締めを選好)の側面も見られた。
据え置きでもいいのではないかと考えていたFOMC参加者は少数存在した
FRBのパウエル議長は9月会合後の記者会見で利下げについて、米労働市場の悪化を前にした「リスク管理の利下げ」と表現した。9月会合前に発表された8月の非農業部門就業者数が前月比で2.2万人の増加にとどまったことなどから米労働市場の変調はあるものの、失業率などは表面的には安定しており、手探りの利下げ再開だった。
今回の議事要旨でも大部分の参加者が10月以降の年内の追加利下げを支持することが前提ながら、次のようにタカ派的な記述も見られた。
まず、「インフレ見通しに対する上振れリスクを重視する参加者が過半数を占めた」との記述だ。ドットチャートを見ると、年内残りの会合(10月、12月)で利下げ1回もしくは据え置きを見込むFOMC参加者は合計9名となる。インフレを懸念するという声は小さくはないようだ。
インフレ懸念についてパウエル議長やニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁らは、最近の発言から警戒心を多少緩和し、焦点を雇用にシフトさせたと筆者はみている。パウエル議長は8月のジャクソンホール会議や、9月のFOMC後の会見でインフレ懸念が多少後退したと述べている。また、ウィリアムズ総裁は9月30日に、それまでの「据え置きが適切」から、雇用とインフレのリスクが拮抗する状況に変化したとして「利下げは理にかなっている」と発言のトーンを変化させた。
一方で、クリーブランド連銀ハマック総裁、カンザスシティー連銀のシュミッド総裁、シカゴ連銀のグールズビー総裁など多くの連銀総裁は利下げに慎重な姿勢と見られる。
次に、議事要旨に戻ると、「数人の参加者が今回の会合で政策金利の据え置きにメリットがあると指摘した。もしくは、そのような決定に賛成していた可能性がある」との記述があり、これもタカ派的と見られよう。図表1のドットチャートでは、9月会合での据え置きを指示したのは1名だが、議事要旨では議論の途中までは据え置きを支持していた人が数名いたことがうかがえるからだ。
最後に、「FOMC参加者は全般に、労働市場の状況を示す最近の指標に急激な悪化は見られなかったと判断した」との記述にも注目したい。9月のFOMC前の状況を思い起こすと、9月月初に発表された8月の米雇用統計の、しかも非農業部門雇用者数の低下から、市場では米労働市場は悪化との見方が優勢で、これを受け利下げの織り込みが進んだところもある。
ただし、雇用者数低下の判断には注意も必要だ。移民流入の減少などで評価基準が変化している可能性があるからだ。過去には非農業部門雇用者数の前月からの伸びが10万人~15万人程度を好不調の目安とすることもあったが、最近ではその水準が低下したとの見方もある。また、労働市場の判断には非農業部門雇用者数の変化だけでなく、失業率など他のデータを幅広く見ることも重要だ。その失業率はじり高ではあるが、概ね安定的とも見られる。市場と当局の認識に差がないのかに注意した。もっとも、政府機関閉鎖で主要な経済指標の発表は延期されており、データでの判断は当面難しそうだ。FOMC参加者のコメントなどから労働市場に対する認識を再確認したい。
最近の興味深いFOMC参加者の提言は会合では検討されなかったようだ
最近、FOMC参加者から興味深い提言があった。1つ目はボウマン副議長が9月26日にFRBはバランスシート(準備金残高)の最小化を目指すべきと述べたことだ。2つ目は25日にダラス連銀のローガン総裁が1980年代から採用されているフェデラルファンド(FF)金利を変えてはどうかというコメントだ。
議事要旨ではバランスシート縮小については、量的引き締め(QT)がこれまでのところ順調に進んでいるという従来の表現にとどまっている。準備預金残高については26年3月末までに2.8兆ドル程度に近づくとの見通しが示されている。しかし、議事要旨に、ボウマン副議長のアイデアが検討された形跡は見当たらなかった。
FRBはコロナ禍などでバランスシートを拡大させ、準備預金残高は「豊富・潤沢な水準」となった。これをQTにより「十分な水準」にまで縮小する過程に現在はあると考えられる。これに対しボウマン副議長は、長期的には、準備預金残高を十分な水準ではなく、むしろ低い水準に傾け、バランスシートを可能な限り小さくすることが望ましいとの考えを講演で指摘した。今回の会合は利下げが主題だったのだろうが、準備預金残高についての今後の議論に注目したい。
ローガン総裁のFF金利を、より利用頻度が高く市場との連動性が高い「トライパーティー一般担保レート(TGCR)などに代えてはどうかというアイデアについては議論をされた形跡が見当たらなかった。現状、FFレートでも金融政策は何とか運営されている中、利下げの議論が最優先だったのだろうか。しかし、ローガン総裁は、その経歴からマネーマーケットなどへの造詣が深いだけに、発言に重みがあると思われる。当面の課題ではないのかもしれないが、今後の展開を注意深く見守りたい。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。