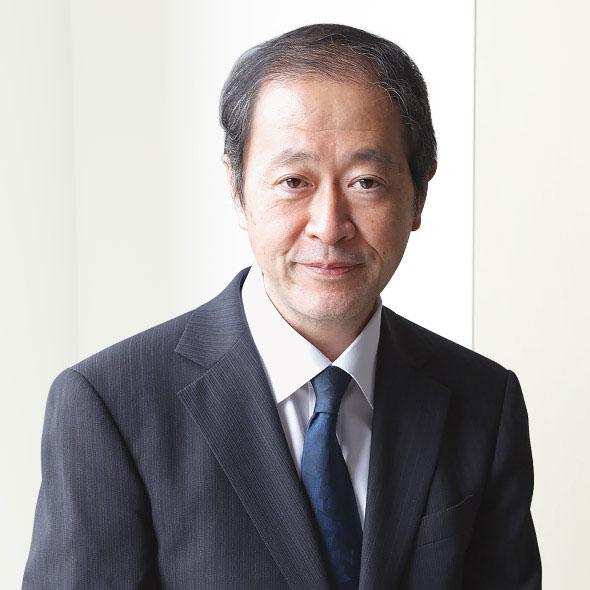- Article Title
- 日銀は想定以上にハト派姿勢だったが、注意も必要
5月1日に終了した日銀の金融政策決定会合で、政策金利の据え置きが決定された。展望レポートではトランプ政権の関税政策による不確実性が影響し、経済成長率と物価見通しが下方修正された。植田総裁の会見でも関税政策による不確実性に懸念を示すなどハト派寄りで、基調的物価が2%に到達する時期が後ずれとも指摘したが、利上げ時期は必ずしも後ずれしない可能性があることを示唆した。
日銀、市場予想通りに政策金利を据え置いたが、全体のトーンはハト派
日銀は5月1日に終了した金融政策決定会合(会合)で、政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.5%に据え置くことを全会一致で決定した(図表1参照)。市場では、トランプ政権の関税政策による不確実性を受け、幅広く据え置きが見込まれていた。
今回の会合では、関税政策による不確実性が日本経済や金融政策にどのように影響すると日銀が判断しているかが焦点であった。そのため、「経済・物価情勢の展望」(展望レポート、2025年4月)や日銀の植田総裁の会見が注目された。全体的な印象は想定以上にハト派(金融緩和を選好)寄りで、会合後に為替市場で円安が進行した。
日銀は展望レポートで、経済成長率、インフレ見通しを概ね引き下げた
今回の日銀の会合のトーンはハト派寄りと市場(そして筆者も)は見ている。注意したいのは利上げ姿勢を放棄したわけではない点だ。展望レポートでは、「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」と述べるなど利上げ姿勢を維持している。しかし、日銀は次の利上げの時期の後ずれを示唆するなど、前回の会合に比べれば明らかにハト派寄りと判断できよう。
展望レポートと植田総裁の会見で、ハト派的と思われる主なポイントを振り返る。
展望レポートは日銀政策委員の見通しが下方修正された点がハト派的だ。経済成長率予想は関税政策の影響で押し下げられており、25年度は前回の1.1%から0.5%へ、26年度は1.0%から0.7%へと、それぞれ下方修正されている(図表2参照)。
物価見通しも下方修正が目立つ。コアCPI(生鮮食品を除いた消費者物価指数)を見ると26年度の物価見通しが1.7%と前回の2.0%から引き下げられ、変動の大きい項目を除いたコアコアCPIも26年度は1.8%に引き下げられた。日銀はこれまで2%近辺での推移を見込んでいたが、関税政策を受け、一旦は2%割れを想定していることが示された。物価の伸びはいったん鈍化し、再び2%に向かうという軌道がメインシナリオとなったことで、追加利上げに慎重になることも想定される。
また、ややテクニカルな話だが、「見通し期間後半」には安定的に2%で推移する、という表現を前回の展望レポートから変更しなかったこともハト派的だ。これは基調的なインフレ率が安定的に2%に達する時期を1年程度遅らせたことを意味するからだ。理由は図表2にあるように、今回の展望レポートでは27年度が予測期間となっているが、前回は展望レポートは26年度までが見通し期間だ。「見通し期間後半」という表現の維持は、物価目標達成時期の後ずれを示唆したと読み取れる。
さらに、今回の展望レポートではリスクバランスもハト派的だ。物価見通し等を引き下げた上に、経済、物価のリスクバランスは25、26年度とも下振れリスクの方が大きいとしたからだ。前回の展望レポートでは25年度の物価リスクは上振れリスクが大きいと指摘されるなど逆方向が見込まれていた。
植田総裁の会見もハト派寄りだったが、利上げ姿勢も残している点には注意
植田総裁の会見もハト派寄りを確認させる内容だった。全体的なトーンを支配したのは「各国の通商政策の展開や影響を巡る不確実性が極めて高い」、という発言だろう。トランプ政権の関税政策の影響を慎重に見守る姿勢が想定される。
展望レポートの見通しの前提については、「関税交渉がある程度進展し、サプライチェーン(供給網)が大きく毀損される状況は回避されることなどを前提に作成した」、ことが明らかにされた。関税交渉が進展し、サプライチェーンの混乱が回避される前提ならば物価への影響は押し下げ方向となることが想定される。しかし、この前提が崩れた場合のリスクはそれなりに大きい。事態の展開を見守ることが必要というメッセージにも聞こえる。
関税の経済・物価への影響を問われ、植田総裁は、「企業収益の減少、不確実性の高まりによる支出の先送りなどの経路を通じて、経済の下押し、物価の伸び鈍化を懸念する」といった内容の回答を述べた。関税の間接的な影響として、日本企業がコスト削減路線という過去のデフレ要因に回帰することがないかを見守ることの重要性を示唆したのだろう。日銀は賃上げに直接関与できるわけではないが、賃金と物価の好循環(奇異な面もある表現と筆者は考えるが)を待ち望む日銀にとり、関税の影響は気が気でないというところか。
今回の植田総裁の会見でおそらく最もハト派寄りと思われる発言は、「基調的な物価上昇率が伸び悩む局面では無理に利上げしない」であろう。基調的な物価上昇率の展開次第だが、当面の利上げ見送りを示唆したようにも感じられる。なお、日銀は基調的な物価上昇率の計測方法について明確に説明していないこともあり、今後のコミュニケーションには細心の注意が必要だろう。
ここまで植田総裁のハト派寄りの発言を振り返ってきた。その中には2%の物価目標の達成時期が「やや後ずれ」する見込みであることも含まれる。しかし、植田総裁は次の利上げについて、「基調的物価が2%に到達する時期はやや後ずれしても、利上げの時期が同じように後ずれするかというと必ずしもそうではない」といった内容を述べていることも重要なポイントだ。利上げの可能性を残すことで、政策の柔軟性をしっかり確保しているからだ。
今回の日銀のトーンを素直に読めば、年内利下げの可能性は遠のいたと考えるのがメインシナリオだろう。しかし、その重要な決定要因は不確実性が高いトランプ関税だ。サブシナリオとして年内追加利上げもそれなりの可能性で残しておくべきだろう。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。