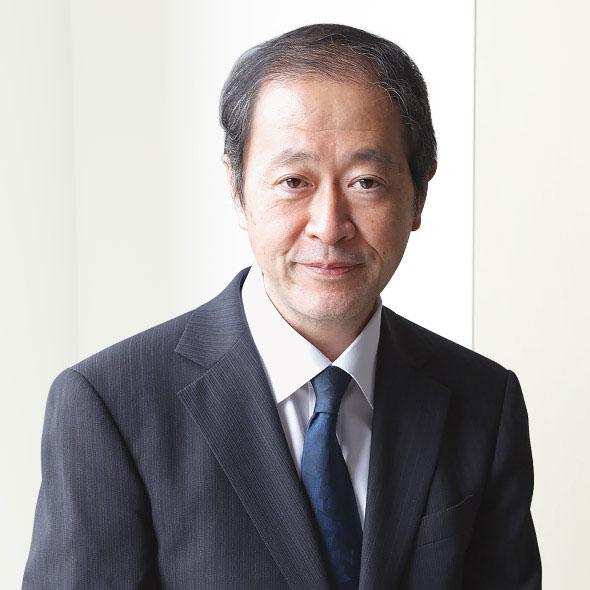- Article Title
- ユーロ圏の妥結賃金急落も、見るべき点は残ってる
欧州中央銀行(ECB)が発表したユーロ圏の1-3月期の妥結賃金は前年同期比2.4%上昇と賃金の鈍化傾向が明らかとなった。賃金とサービス価格の連動性から、賃金の落ち着きは物価の鈍化が示唆される。市場は年内に2回よりは3回の利下げを見込み始めたようだ。ただし、ユーロ圏のインフレ動向はアップサイドリスクもあるうえ、トランプ関税の影響は不確実で、見守る姿勢が必要と見ている。
1-3月期のユーロ圏の妥結賃金はピークから急低下
欧州中央銀行(ECB)が5月23日に発表した1-3月期のユーロ圏の妥結賃金は、前年同期比2.4%上昇と、24年10-12月期の4.1%上昇、ピークとなった7-9月期の5.4%上昇を下回った(図表1参照)。19日に発表されたユーロ圏の4月の消費者物価指数(CPI、改定値)は前年同月比が2.2%上昇と、3月の2.2%上昇に一致するも物価目標に向けインフレが鈍化傾向であることが示唆された。
総合CPIは、構成指数であるサービスCPIが4%前後で高止まりしているため、鈍化ペースが遅れていた(図表2参照)。賃金とサービスにある程度の連動性もみられることから、賃金の落ち着きはユーロ圏の物価を鈍化させることも想定させる。
ユーロ圏のインフレは鈍化傾向継続がメインシナリオだが注意も必要
ユーロ圏の妥結賃金はカバレッジの低さや速報性に欠ける点などの問題点が指摘されている。しかし、ECBは雇用サービス会社の賃金データなどを活用して速報性をカバーしていると説明している。ECBはそれらのデータを活用していることから賃金鈍化についてある程度の確信はあったと見られる。
それでも1-3月期の妥結賃金の2.4%という伸びは「上出来」だろう。市場はECBの利下げの織り込み度合いを強め、年内2回程度の利下げから、3回の利下げをより強く意識し始めたようだ。筆者も年内2回程度の利下げは見込むが、3回以上の利下げを見込むには至っていない。
まず、ECBがインフレ率の動向を知るうえで重視する「基調的インフレ率(PCCI、インフレ動向の共通成分を抽出して作成)は4月が2.2%と前月から横ばいだった。PCCIは昨年、2%を下回る局面もあったことに比べれば、鈍化のペースは緩んでいる。22日に発表された4月のECBの政策理事会の議事要旨でも、メインシナリオはあくまでインフレ鈍化ではあるが、PCCIを念頭に上振れリスクへの注意も一応は必要と指摘している。
次にテクニカルな要因だが、失業率とインフレ率の関係(フィリップス曲線)の平たん化を指摘する声もある。横軸を失業率、縦軸にインフレ率をとった曲線で両者の関係を見ると、足元の曲線は平たんとなっている。これは、「失業率が上昇しても、インフレ率が下がりにくい」傾向を示唆する。この平たん化を前提とすれば、足元、「インフレ率を低下させるには、ユーロ圏の景気後退の水準にまで悪化させる必要がある」とも読み替えられる。
しかしユーロ圏の景況感はそこまで悪化していないようだ。コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻後にユーロ圏の主な景況感指数は景気後退の水準にまで悪化した(図表3参照)。独Ifo企業景況感指数の期待指数やZEW期待指数が大幅に低下した時期が相当する。足元でも、トランプ関税による景気への悪影響が懸念され下ぶれた。しかし、景況感指数には底堅さも見られ始めた。欧州の軍備強化などをテーマとした財政拡大による下支えと、トランプ関税がそれほど厳しいものではないと市場に見透かされたことが改善の背景と見られる。
そのうえ、ユーロ圏の1-3月期のGDP(国内総生産)成長率は前年同期比で1.2%増と、力強さはないが、プラス成長をきっちりと確保している。ECBが3月に示した25年の成長予想(0.9%)を上回っており底堅いとも見られる。そのため景気悪化で失業率が上昇、インフレが鈍化する可能性はやや後退したようだ。
ユーロ高やエネルギー価格の下落傾向など、他の要因を考えれば、ユーロ圏のインフレ動向のメインシナリオは依然として鈍化継続だと筆者も考えてはいるが、これまで指摘してきた点は、アップサイドリスクとして注意も必要だ。
ユーロ圏の金融政策の今後を占ううえで、関税政策の不確実性は高い
ユーロ圏のインフレ動向のうち、最大の不透明要因はトランプ関税の行方だろう。先週末、トランプ大統領は欧州連合(EU)との貿易赤字は容認できず、交渉も遅いことからEUからの製品に6月1日から50%の関税を課す方針を示した。しかし、欧州委員会のフォンデアライエン委員長との電話会談後、EUに対する50%の関税発動期限を7月9日まで延長すると25日に表明した。
ECBが先の議事要旨で示した関税のインフレに対する影響は様々な論点を指摘している。その意味で評価は定まっていない面もあるが、景気抑制やユーロ高、エネルギー価格の下落など概ね物価下押し方向の要因が、サプライチェーンの混乱など物価押し上げ要因を短期的に上回ると見ているようだ。足元でもECBメンバーの多くが6月の政策理事会での利下げを支持しているようだ。
ただし、この週末の米国とEUのイベントはトランプ関税が市場に配慮する側面と同時に、米国に対し貿易黒字を計上するEUとの関税交渉は簡単ではないことも示唆された。関税交渉の行方は不確実性が高いように思われる。筆者がECBの利下げ回数を2回程度としているのは、3回があり得ないわけではなく、不確実性が高いからに過ぎない。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。外貨建資産の場合は為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。記載内容は作成日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。また、過去の実績は、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
●投資信託は預金等ではないため、元本および利回りの保証はなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料の内容は、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を目的としたものではありません。
●当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト 「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。