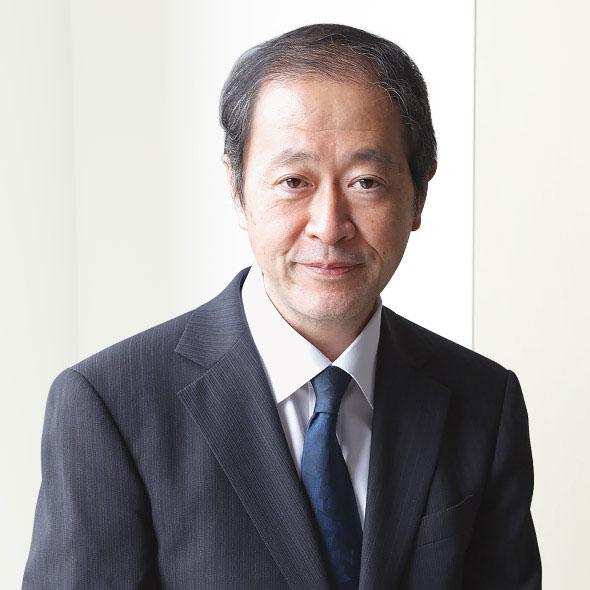- Article Title
- 12月FOMCブラックアウト期間前の気になるポイント
米連邦準備制度理事会(FRB)のベージュブックによると、米経済活動は前回の評価からほぼ変化はないと指摘し、個人消費や雇用に懸念が残る一方で、、物価は緩やかに上昇と指摘している。このような状況下、12月FOMCでの利下げ判断に決め手は探しにくいが、ニューヨーク連銀総裁らの発言は利下げ方向へ作用したようだ。なお、来年の利下げ見通しについては確認すべきポイントが残されている。
12月FOMC前のベージュブックは新規材料に乏しかった
米連邦準備制度理事会(FRB)が11月26日に公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)によると、米経済活動はここ数週間、ほとんど変化が見られなかった。全体報告によると、個人消費は高所得層を除いてさらに減少したと指摘している。雇用についてはわずかに減少し、物価は関税などの影響で緩やかに上昇したと述べられている。
FRBは12月9日~10日に米連邦公開市場委員会(FOMC)の開催を予定している。今週末(11月29日)から、金融当局が公に金融政策に言及しないブラックアウト期間となる。市場は12月FOMCでフェデラルファンド(FF)金利が引き下げられる確率を8割程度と見ている(図表1参照)。
12月FOMCにおける参加者の見解は追加利下げに対し一枚岩ではない
ベージュブックが発表され、12月FOMCを前に金融当局からの情報発信は、マスコミによるリークなどを除けば、概ね出尽くした。あとは9月分の個人消費支出(PCE)などの経済指標の発表が残るのみだ。なお、11月の米雇用統計等は政府機関閉鎖の影響で発表は12月16日とFOMC後となる。
10月のFOMC後の記者会見でFRBのパウエル議長は「12月会合での追加利下げは既定路線ではない」と語ったことや、タカ派(金融引締めを選好)的な連銀総裁の発言を受け(図表2参照)、12月のFOMCにおける利下げ見通しは11月半ばには3割前後にまで低下した。しかし足元では12月の追加利下げ見通しが急速に回復している。
追加利下げの確度が高まった背景をFOMC参加者の発言から眺めると、ニューヨーク(NY)連銀のウィリアムズ総裁のハト派(金融緩和を選好)発言の影響が大きかったようだ。ウィリアムズ総裁は雇用の下振れリスクが高まっている一方、インフレの上振れリスクは和らいでいるとして利下げを支持した。ウィリアムズ総裁は、パウエルFRB議長と歩調を合わせる傾向があることも発言の影響力を高めたとみられる。サンフランシスコ連銀のデーリー総裁もパウエル議長と同調する傾向が知られている。デーリー総裁は11月半ばまで12月の追加利下げについての判断に迷いを見せていた。パウエル議長の既定路線ではないという発言を連想させる姿勢だった。しかし、足元、利下げ支持に傾いた。
一方、図表2でグレーに色づけした連銀総裁に加え、ダラス、ボストン、カンザスシティの各連銀総裁らは、これまでの発言から判断して12月は据え置きを支持する可能性がある。しかし、投票権なども加味すると、過半数に届くかは微妙だ。
ウォラー理事はボウマン理事と共に、雇用市場への懸念から12月利下げを支持していた。ただし、ウォラー理事は来年のFOMCでは会合ごとに判断すると述べている。市場は来年3回程度の利下げを見込んでいるが、ウォラー理事の発言からは利下げパスはそれほど明確でない。影響力が大きいウォラー理事の発言だけに注意は必要だろう。
決め手とはなりにくいが、米経済指標の一部は利下げ支持要因だろう
12月FOMCの追加利下げの確度を高めた可能性がある経済指標として、4.4%とじり高傾向を示した9月の失業率、消費者信頼感指数の悪化等が挙げられる。米調査会社コンファレンス・ボードが25日に発表した11月の米消費者信頼感指数は88.7と10月の95.5(改定値)を大幅に下回り、トランプ関税で急速に消費者心理が悪化した4月の水準に迫った(図表3参照)。構成指数をみると先行きを示唆する期待指数の悪化が影響した。米国の消費は夏過ぎまでは堅調であったが、やや先行きに不安が残る調査内容だ。
ただし、同調査の別の質問項目で消費者の懸念内容を見ると、雇用への不安が根強い一方で、物価上昇への懸念も根強く、消費を慎重にしているようだ。米消費者信頼感指数は金融政策の判断の難しさを象徴するような結果となっている。
来月のFOMCで追加利下げはあるだろうか。筆者の答えは「利下げの可能性が高い}だ。ここまで述べてきたFRBのコミュニケーションにより市場の利下げ期待が相当高まっていること、ベージュブックの内容は労働市場に懸念を示す一方で、物価に対しては若干表現を和らげたこと等が主な要因だ。11月に変調を見せた資産市場を利下げ期待が下支えしたことも要因として挙げられる。ただし反対票(据え置き支持)も多いだろう。
一方で、来年の見通しについては、確認したい点が残されているため、市場の3回利下げ予想ほど筆者は明確に織り込めていない。当面の確認ポイントとしては、経済指標(特に11月の米労働統計とインフレ指標)は当然ながら、感謝祭後の年末商戦の動向、次回FOMCにおける26年末の政策金利水準(ドットチャート)等を確認したい。
忘れてはならないのは、おそらく年内に目途がつくと思われる時期FRB議長の人事だが、トランプ大統領の政策ゆえ、こちらについては結果を待つことに専念したい。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。外貨建資産の場合は為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。記載内容は作成日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。また、過去の実績は、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
●投資信託は預金等ではないため、元本および利回りの保証はなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料の内容は、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を目的としたものではありません。
●当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト 「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。