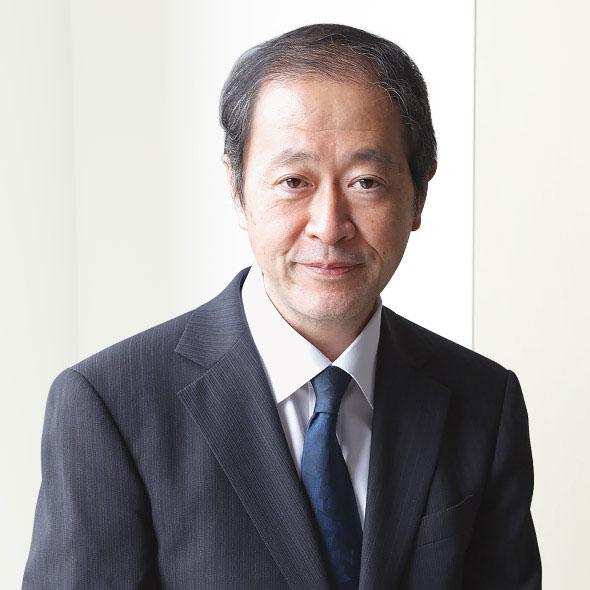- Article Title
- 7月毎月勤労統計、実質賃金プラスの維持が大切
厚生労働省が発表した7月の毎月勤労統計によると、名目賃金は前年同月比4.1%増と市場予想を上回り、実質賃金も0.5%増加した。特別給与の伸びが大きく寄与し、今後はこの効果が薄れる見通し。日本の物価は足元鈍化傾向にあるが、持続的な実質賃金のプラスには賃金の着実な上昇が必要。日銀の追加利上げ時期は短観や関税の影響を見極めつつ、12月または来年1月が有力と考えている。
7月の毎月勤労統計は特別給与を主な押し上げ要因に市場予想を上回る
厚生労働省が9月5日に発表した7月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、定期給与と特別給与の合計で、名目賃金を示す現金給与総額は41万9668円となり、前年同月比では4.1%増えた(図表1参照)。市場予想の3.0%増、6月の3.1%増(確定値)を上回った。サンプルの影響を受けにくい共通事業所ベースのうち、一般労働者の所定内給与は2.4%増と前月の2.3%増を上回った。
物価変動の影響を除いた実質賃金(消費者物価総合指数、帰属家賃を除いたベース)は前年同月比で0.5%増え、市場予想の0.6%減、前月の1.3%減を大幅に上回った。
実質賃金を押し下げてきたインフレには、足元鈍化もみられるが
7月の毎月勤労統計で現金給与総額は前年に比べ4.1%伸びたが、背景は、決まって支給する給与が2.6%増であったのに対し、夏のボーナスに相当する特別給与が7.9%増と想定外に伸びたことが主因である。名目賃金の寄与度分析を見ると伸びの58.5%、約6割が特別給与で説明される。ボーナスが終わる8月には、特別給与による寄与は大幅に低下するのが通例であるため、来月にはこの押し上げ効果が消失すると見られる。
図表1からも明らかなように、7月の実質賃金がプラスに転じたのはこの効果が大きい。ただし、この季節的な効果だけで実質賃金のプラスを持続させることは困難だろう。インフレ(図表2参照)の落ち着きと、賃金の着実な上昇の組み合わせが欠かせないと見られる。
毎月勤労統計では実質賃金の算出に従来から消費者物価指数(CPI:持ち家の家賃換算分である帰属家賃を除いた総合)を使用している。7月の上昇率は3.6%と、6月の3.8%上昇を下回ったが、物価目標の2%を大幅に上回ったままである。
なお、厚労省は今年の3月分から、国際比較のためとして、実質賃金の算出にCPIの総合指数を使う新方式を導入し併記している。7月の総合CPIが3.1%上昇であったことから、こちらのベースで算出した実質賃金は1.0%上昇と、従来ベースの0.5%上昇より改善したようには見える。
日本のCPIの上昇の主因は食料品価格の上昇だが、食料品価格は昨年から上昇が始まっており、図表2にあるように足元は鈍化傾向だ。日銀が指摘するように、今年後半も鈍化傾向が想定される。しかし、その後は再びインフレ率は上昇が見込まれている。食料品価格上昇の反動による物価の鈍化だけに実質賃金の改善(上昇)を期待するのではなく、適切な物価対策も必要だろう。
日銀は追加利上げ姿勢を維持、賃金と物価が利下げ時期を左右しそうだ
持続的な実質賃金のプラスを今後実現するには賃金の伸びが欠かせない。そこで、基本給に相当する所定内給与を一般労働者(サンプルベース)についてみると7月は前年同月比で2.8%増と、前月の2.6%増を上回った。また、共通事業所ベースで一般労働者の所定内給与は7月が2.4%増と、こちらも前月の2.3%増を上回った。調査方法により賃金の伸びに多少の違いはあるとしても、今年の春闘の高水準の賃上げ妥結を反映したと見られよう。
今回の毎月勤労統計は日銀の追加利上げの決め手とはならないとしても、後押しする材料となりそうだ。最近の日銀メンバーの発言(図表3参照)を参考に、今後の注目点を考える。
日銀の植田総裁はジャクソンホール会議で「技術と労働市場」をテーマに行われたパネル討論会で「賃金には上昇圧力がかかり続ける」と発言している。労働力不足を念頭にした発言であり、賃金上昇圧力について長期的視点でとらえているようだ。
ただし次の利上げ時期を判断するうえでは来年の春闘でも賃上げが確保されるかの短期的な見極めも重要だ。春闘の結果が出る来年春以降まで必ず待つわけではない。賃上げの確度が高まれば利上げの環境は整うと過去に植田総裁は指摘した。そうした中、中川委員は10月1日に発表される短観、氷見野副総裁もヒアリング情報の重要性を指摘している。短観で賃金を直接問うわけではないとしても、関連する質問項目も多く、目先は短観が注目材料だろう。なお、氷見野副総裁は関税の不確実性が依然大きいと指摘したこともありハト派(金融緩和を選好)寄りの発言と市場は解釈した。しかし、トランプ米大統領は4日に日本との貿易合意を実施する大統領令に署名し、最大15%の関税を課すことなどが確認された。この合意が日銀の不確実性への懸念をどこまで解消するのかわからないが、この点についての日銀メンバーの今後の発言にも注目したい。
短観を確認する必要があることから追加利上げは10月以降と筆者は考えるが、政治状況や関税の影響の評価などを踏まえると最初は12月か来年1月会合が追加利上げ再開の時期になるのではないだろうか。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。