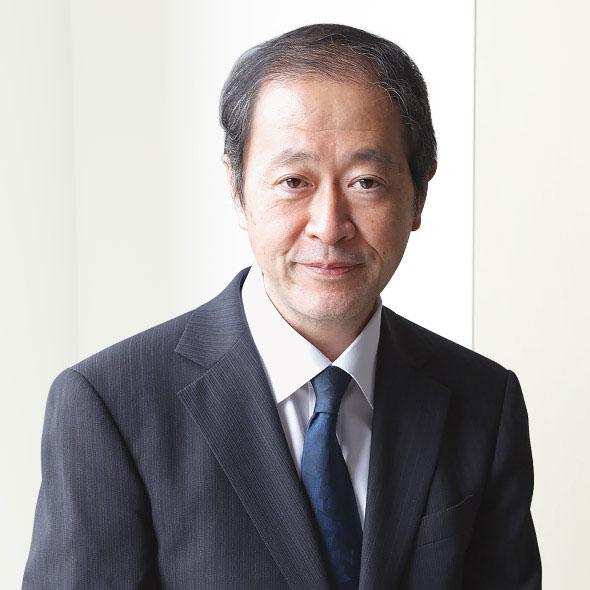- Article Title
- トランプ政権とFRB独立性を巡る攻防の注目点
トランプ米大統領は、住宅ローン不正疑惑を理由にFRBクック理事の解任を発表し、両者の間で法廷闘争が始まった。FRB理事会の構成やFOMCの投票権の仕組みから、トランプ派が理事会で過半数を占めても金融政策への影響は足元限定的にも見えるが、中央銀行の独立性などへの政治介入は深刻なリスクだろう。今後の司法判断や仮差し止め命令、地区連銀総裁の任命手続きなどに注視が必要だ。
米政権からの利下げ圧力が強まる中、米国債イールドカーブはスティープ化
トランプ米大統領は8月25日、住宅ローン関連の不正疑惑があるとして米連邦準備制度理事会(FRB)のクック理事を解任すると発表した。現地の報道などによると大統領がFRB理事の解任を試みるのは110年以上に及ぶFRBの歴史で初めてとのことだ。トランプ大統領のクック理事に対する解任の通知に対し、FRBは26日に声明を発表し、裁判所の判断に従う姿勢を示した。
FRBに利下げを求めるトランプ大統領がクック理事に解任を通知した後、米国債市場では利下げ期待を反映して2年国債利回りが低下する一方で、30年国債利回りは上昇、利回り格差(スプレッド)は拡大した(図表1参照)。
FRB理事会(議長、副議長、理事)の過半がトランプ派となる懸念
FRB理事会(議長、副議長、理事)の構成を確認すると、7名が原則だが8月8日にクーグラー氏が辞任したため1名空席で6名となっている(図表2参照)。空席にはミラン米大統領経済諮問委員会(CEA)委員長が指名された。
7月の米連邦公開市場委員会(FOMC下げを求めて反対票を投じたボウマン副議長と、ウォラー理事(共に第1次トランプ政権で指名)とミラン氏に加え、現在話題となっているクック理事の枠がトランプ派となると、FRB理事会7名のうち、4名がトランプ寄りとなる可能性がある。
もっとも、FOMCの決定(投票権)は理事会の7名に加え、12名の地区連銀総裁のうち、持ち回りで5名が投票権を持つため、基本的に合計12名の投票で金融政策が決定される仕組みだ。また、投票権を持たない7名の地区連銀総裁も、FOMCの金融政策の議論には参加することから、現状の経済動向から判断して非合理的な利下げを求めても、無理が通せないかもしれない(ただし、この点についてのリスクは後述する)。
理事会の7名は、FOMCで常に投票権を持つなど、影響力が大きい。仮にクック理事の後任にトランプ大統領の意向に沿う理事が選ばれ過半数を占めた場合、金融政策への影響は小さくはないだろう。ただし、FOMC全体の構成を考えれば、当面の影響は限られるかもしれない。図表1に示したように(無理な)利下げと、それに伴うインフレ懸念による長期債利回りの相対的な上昇はみられるが、小幅な反応にとどまっている。現時点の状況を冷静に判断してのことと思われる。
クック氏への攻撃はFRBの独立性を脅かす恐れがある
それでもリスクは残る。中央銀行の独立性に対する政治介入への懸念だ。歴史的教訓として、中央銀行には(政治から)緩和的な金融政策運営を求める圧力がかかりやすい。このような事態を避けるのが中央銀行の独立性で、通常2つの側面があるとされている。
1つ目は金融政策の運営主体としての独立性で、中央銀行が金融政策を中立的・専門的に(政府から独立して)判断するというものだ。
2つ目は中央銀行メンバーの身分の保全(任期や不当に解任されない、など)に関するものだ。クック氏を含め図表2に示したFRB理事会の7名は議長や副議長などのポストがあるが、全員FRB理事でもある。トランプ大統領のFRBへの圧力の中、市場で注目されたのは連邦準備制度法10条で、「大統領が『正当な理由』により早期に解任しない限り、各理事は前任者の任期満了から14年間の任期を務める」といった内容となっている。
注目は『正当な理由』が何かということだ。これがなければ大統領であってFRB理事を解任できないことになる。「正当な理由」とは①職務の非効率(無能な当局者による無駄な運営)、②職務怠慢,③不正行為(職務執行中に他社に損害を与える不正な行為)が想定されているようだ。
FRBのクック理事は8月28日、住宅ローン申請に関する不正疑惑を理由に自身を解任しようとしているトランプ米大統領に抗議し、ワシントンの連邦裁判所に提訴した。中央銀行の独立性を巡り、FRBと政治との法廷闘争が開始されたこととなる。今後の重要な争点は解任の理由に挙げた住宅ローン申請が『正当な理由』に該当するかであろう。
トランプ大統領によるFRBへの圧力はパウエル議長を標的としたこともあった。FRB本部の改修工事費用が巨額となったと批判した。米行政管理予算局(OMB)は7月に改修工事は(フランスの)ベルサイユ宮殿のように豪華だと批判した。トランプ大統領は8月12日に自身のSNSでパウエル議長への批判を続けたが、工事費用の見積額の数字に疑問の残る内容だった。明確だったのはその投稿の冒頭で利下げを求めていることだ。工事費用の増加は建築資材の高騰なども反映しており、解任の 『正当な理由』となるのか疑問も残る。
一方、クック理事への解任圧力は2021年に2つの住宅を購入した際、投資用ではなくどちらも居住用として優遇ローンを組んだことが不正にあたると指摘している。これに対しクック理事は訴訟を開始するとともに、トランプ氏による解任が効力を持たないよう、仮差し止め令の発令を連邦地裁に提出した。クック理事の弁護士は、住居の目的を誤って記載していた可能性があったとしても、それが故意でも重要なものでもない限り、『正当な理由』に該当するような『違反行為』ではない」と、仮差し止め命令を求める訴状に記したと報道されている。
今後の判断は司法にゆだねられた格好だが、目先の注目は仮差し止め命令の取り扱いだろう。
地区連銀総裁に圧力がかかる可能性もあり、今後の展開に注視が必要
クック氏の今後については司法の判断を待つ必要があるが、展開によっては別のリスクにも注意する必要がある。
先日、ブレイナード元副議長は今回のクック理事の問題は理事個人の問題でなく、FRBの独立性への攻撃の可能性を指摘している。
図表2で示したように、FOMCの投票権は7人の理事に加え、12の地区連銀総裁のうち輪番(ニューヨーク連銀は常に投票権がある)で投票権を持ち回りしている。地区連銀総裁の投票権を加えれば、仮に理事会がトランプ派で過半を占めても、FOMCで金融政策を決定する投票権では過半数とならないことは安心材料に見える。
しかし、地区連銀総裁の指名や再任の手続きに不安が台頭してきた。各地区連銀総裁は、FRB理事と異なり、ホワイトハウスの指名や上院の承認を受けずに選出される。問題は任期または再任の手続きにある。地区連銀総裁の任期は5年だが、1または6で終わる年の2月末に終了する。通常は、総裁が続投の意思を示せば再任される、いわば形式的なものと思われていた。次の任期切れは26年2月だ。仮にトランプ氏を支持する多数派の理事会であった場合、各地区連銀総裁は再任の手続きに際して、金融政策について絵踏みをさせられる恐れがあるかもしれない。ブレイナード元副議長は、このようなリスクを指摘したのだろう。
FRBが現体制であっても、9月のFOMCで利下げをする可能性は高いと思われる。それでもFRBに対して攻撃の手を緩めないトランプ大統領が金融政策で何を求めているのかは不明だ。利下げだけではコントロールできない長期債利回りの押し下げや、さらにはFRBを意のままにすることを目指しているのだろうか。トランプ大統領の圧力は利下げのための脅しというレベルではない可能性もあるだけに、今後の展開には注視が必要だ。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。外貨建資産の場合は為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。記載内容は作成日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。また、過去の実績は、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
●投資信託は預金等ではないため、元本および利回りの保証はなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料の内容は、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を目的としたものではありません。
●当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト 「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。
手数料およびリスクについてはこちら
ディープ・インサイトの記事一覧
| 日付 | タイトル | タグ |
|---|---|---|
|
日付
2026/02/26
|
タイトル リフレ派とされる2名の日銀人事提案と金融政策 | タグ |
|
日付
2026/02/26
|
タイトル 長期金利上昇のリスクシナリオ:過去事例からの検討 | タグ |
|
日付
2026/02/24
|
タイトル 関税敗訴 トランプ大統領の次の一手 | タグ |
|
日付
2026/02/16
|
タイトル 政府債務対GDP比率は減るのか? | タグ |
|
日付
2026/02/12
|
タイトル 自民大勝は日経平均6万円超えの号砲か? | タグ |
|
日付
2026/02/09
|
タイトル 圧勝した高市首相の難敵 | タグ |
|
日付
2026/02/03
|
タイトル FRBの政策を左右する3つのポイント | タグ |
|
日付
2026/01/27
|
タイトル 日本株の行方 | タグ |
|
日付
2026/01/20
|
タイトル 米銀行決算の裏に潜むリスク | タグ |
|
日付
2026/01/15
|
タイトル 高市首相の解散で政権選択選挙へ | タグ |